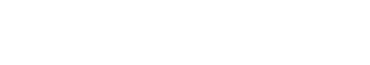社会保険の基礎と仕組みを解説
2025.02.19
お役立ち情報

会社の経営における「社会保険」とは、どのようなもので、どのような手続きが必要なのか、気を付けなければならないことは何なのか、について解説します。
社会保険の基礎
社会保険とは、狭い意味では、医療保険である健康保険と年金保険である厚生年金をさします。それに対し、広い意味での社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の5種類のことをいいます。
健康保険とは
病気やケガ、それに伴う休業、出産や死亡といった事故に備えて生活の安定を図る公的医療保険のことです。健康保険組合と全国健康保険協会の二つの運営機関が存在しますが、この二つの医療保険を組み合わせた総称であり、サラリーマンなど企業に勤めている人とその家族が加入する制度のことを指します。
介護保険とは
65歳以上の高齢者、又は40~60歳の特定疾病患者は、介護が必要になった場合に介護サービスを受けることが出来ます。
40歳以上の人は、被保険者として介護保険に加入し介護保険を毎月支払うことになっており、この保険料が介護保険サービスを運営していくための必要な財源になっています。
厚生年金保険とは
公的年金には、国民年金と厚生年金があります。厚生年金はいわば国民年金の2階建て部分に相当し、国民年金の上乗せ部分になります。
厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤める70歳未満の会社員及び公務員が加入する公的年金制度で、原則として全員が定額の保険料を支払う国民年金とは異なり、厚生年金の保険料は収入額に応じて変わります。
雇用保険とは
労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図ること、再就職の援助を行うことなどを目的とした制度です。社会保険とは加入対象となる労働者の要件が異なる点に注意が必要です。
労災保険とは
労働者災害補償保険のことで、業務上の事由や通勤による労働者のケガや病気、また死亡に対してその労働者又は遺族に対し必要な補償を行う制度のことです。
社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
社会保険の仕組みについて
社会保険を端的に表現すると、みんなでお金を出し合って万が一に備え事故があった場合にお金を支給する制度をいい、国が運営する形式をとっています。
医療保険は病気やケガに対して、厚生年金及び国民年金は老後の生活に備えて、介護保険は介護状態となったときに、介護サービス利用料を負担します。
雇用保険は、主に労働者の失業に対して、労災保険は労働者の労務に起因するケガや疾病に対して保証する制度と分類することができます。
ここからは、狭い意味での社会保険(健康保険及び厚生年金)の適用条件についてみてみましょう 。
強制適用事業所とは
国や法人の事業、個人事業のうち一部の業種を除いた常時5人以上の従業員を雇う事業所は、社会保険に必ず入らなければならない事業所で、事業主や労働者の意思にかかわらずに加入の義務があります。
任意適用事業所とは
強制適用事業所以外の事業所で、厚生労働大臣の認可を受けることで社会保険への任意加入が認められる事業所です。
社会保険に加入するメリット
①傷病手当金や出産手当金が受給できる。
業務外の理由による病気やケガ、また出産に対してこれらの理由により会社を休まなければならない場合に受給できます。支給額は賃金の3分の2程度で、支給期間は が開始日から最長1年6ヵ月です。
②老齢年金が増える
社会保険に加入することで「全国民共通の基礎年金」と「報酬比例の厚生年金」の両方を受け取ることができます。
③障害年金と遺族年金が増える
被保険者が障害要件を満たした場合、もしくは死亡した場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金にプラスして障害厚生年金、遺族厚生年金が支給されます。
④保険料の負担
国民年金と国民健康保険はそれぞれ全額被保険者が負担します。一方、健康保険と厚生年金では被保険者の負担が半分になることで、被保険者にとっては大きなメリットになると言えます。
会社の経営において「社会保険」は欠かせない手続きです。
無保険となっていないか、対象者が漏れなく加入しているか、本来受け取れる給付の申請手続きができているか、手続きの代行や、パート従業員の加入の判断などは弊法人にお任せください。